離婚は結婚しているすべての人に考えられる出来事であり、再婚も特別なことではなくなってきました。新しいパートナーとの再婚を考える場合に、離婚から再婚までどのくらい期間を空けたら良いのか、子どもの戸籍や養育費はどうするべきなのかと悩む人も多くいます。
結論から言うと、再婚だからこそ新しいパートナーとの将来や、子どもがいる場合は戸籍や苗字、養育費などについて慎重に考えることが大切です。本記事では、再婚する場合に知っておきたいポイントについて、詳しく解説します。
- 離婚や再婚する人の割合は近年減少傾向にある
- 日本では再婚禁止期間の制度が廃止されたが外国籍の人と結婚する場合には注意が必要
- 子どもがいる場合の再婚は養子縁組をする・しないによって戸籍や苗字、養育費に影響がある
- 再婚には経済的・精神的な安定感を得られるメリットがある反面デメリットも存在する
離婚と再婚の割合や状況はどう?
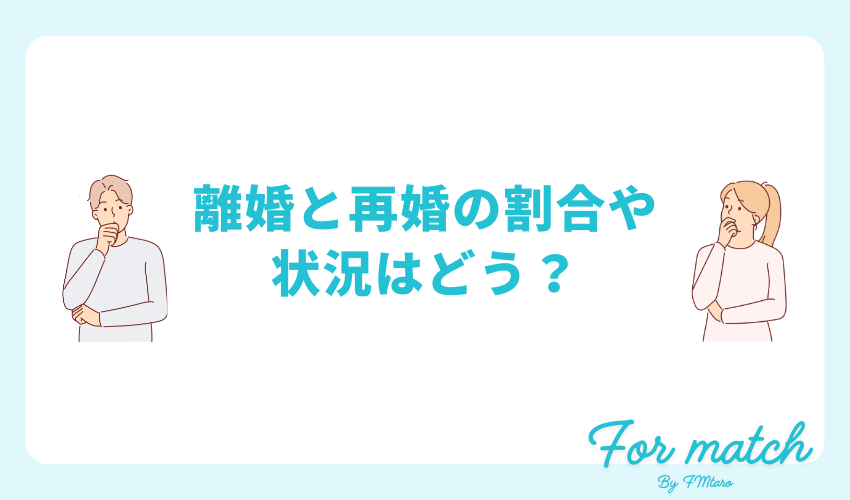
日本人の約3人に1人が離婚していると言われており、未成年の子どもがいながら離婚するケースは、全体の約6割を占めています。再婚する男女の割合は減少傾向で、再婚者は婚姻した約4人に1人の割合です。
本章では、離婚や再婚の割合と状況について解説します。
離婚の割合や状況
令和5年の離婚件数は、厚生労働省の発表によると18万3,808組で、前年より約4,700組多く離婚している結果となりました。令和5年の離婚率は1.52で、令和4年の1.47と比べると0.5増加しています。
離婚件数を年ごとの推移で見ると、近年は減少傾向です。昭和35年から平成14年までの離婚件数は増加傾向でしたが、平成15年以降は微妙な増減を繰り返しながらも、減少の一途をたどっています。
令和2年の離婚件数は約19万3,000組であるため、令和5年は大幅に減少していることがわかります。
参照:厚生労働省『令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況』
参照:厚生労働省『令和4年度「離婚に関する統計」の概況 人口動態統計特殊報告』
再婚の割合や状況
男女における再婚の割合は、昭和48年以降上昇傾向でしたが、平成2年から平成5年には減少しています。その後再び上昇し、令和2年からは減少傾向です。
男性の再婚率は令和2年に19.4%、女性は男性よりも低い16.8%です。令和4年における男性の再婚までにかかる期間は、1年未満が13.7%、5~6年未満が6.6%、10年以上は22.2%となっています。
一方で女性が再婚までにかかる期間は、1年未満が11.8%、5~6年未満が6.5%、10年以上が26.2%となっています。
参照:内閣府男女共同参画局『結婚と家族をめぐる基礎データ』
参照:政府統計『令和4年人口動態統計』
参照:政府統計の総合窓口『前婚解消後から再婚までの期間別にみた夫-妻・年次別再婚件数百分率(各届出年に結婚生活に入り届け出たもの)』
離婚後すぐ結婚できる?再婚禁止期間について解説
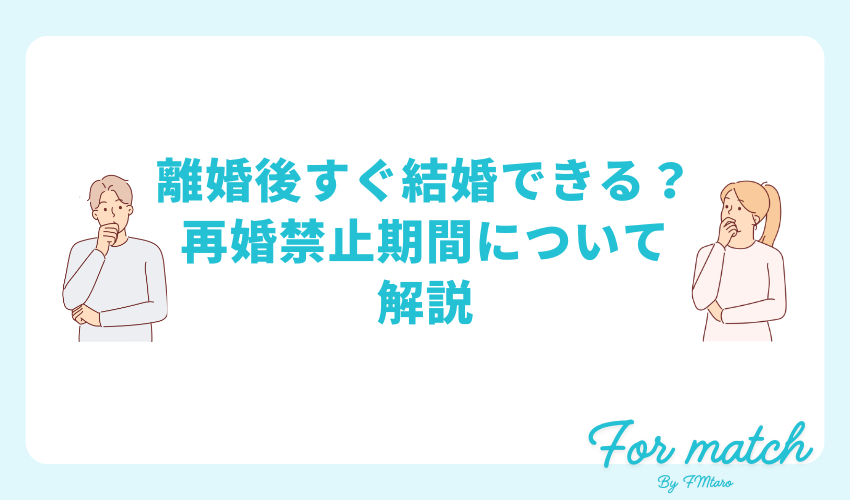
令和6年4月以前は、女性が離婚後すぐに結婚することを法律で禁じられ、再婚までの期間(再婚禁止期間)が設けられていました。これは、元夫と新しい夫の両方の条件に当てはまる子どもができないために設けられたものです。
平成28年6月1日、再婚禁止期間が6カ月から100日へと改正されました。女性は前婚の解消または取り消し日から起算して100日間空ければ、再婚できるようになったのです。
令和6年4月1日には再婚禁止期間が廃止され、女性の自由度が広がりました。加えて、婚姻解消後300日以内に生まれた子どもについては、再婚相手の子どもと推定することになりました。
ただし、再婚禁止期間に定めがある外国籍の人との再婚の場合は、相手の国のルールに従う必要があるので注意しましょう。
参照:法務省『民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について』
参照:法務省『民法等の一部を改正する法律について』
自分に子どもがいる場合に離婚後再婚するときの注意点
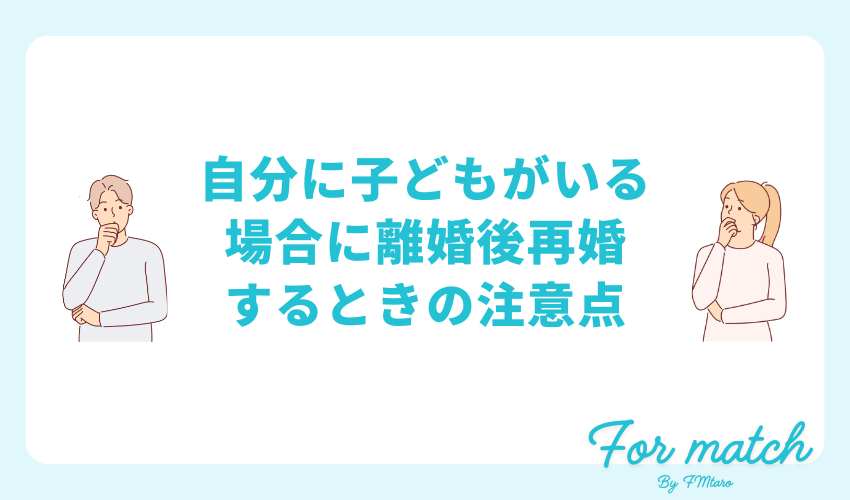
離婚後に新しいパートナーと再婚するときに、自分に子どもがいる場合は気を付けるべき点があります。本章では離婚時や再婚時の子どもの戸籍と苗字、養育費などに関する注意点について解説します。
- 離婚時の子どもの戸籍と苗字について
- 離婚後に再婚したときの子どもの苗字は?
- 再婚に伴う養育費への影響
- 相続への影響
離婚時の子どもの戸籍と苗字について
離婚した場合、妻は夫の戸籍から抜けると、自動的に婚姻前の戸籍・姓へ戻ります。しかし、子どもの戸籍は手続きを踏まなければ夫のところに残ったままです。
母親が親権者になった場合、子どもの戸籍や苗字を変更するには、家庭裁判所で手続きをする必要があります。子どもの住所地を管轄する家庭裁判所で「子の氏の変更許可の申し立て」を行い、許可を得ましょう。
家庭裁判所からの許可が出たら、本籍のある市区町村役場にて母親の戸籍へ子どもの戸籍を移動させます。戸籍の移動が完了すれば、子どもも母親と同じ苗字になります。
離婚後に再婚したときの子どもの苗字は?
子どもがいる人が再婚する場合、新しいパートナーと養子縁組するかしないかが、子どもの苗字に関係します。そのため、再婚前に子どもの戸籍や苗字について考えておくことが大切です。
新しいパートナーと子どもが養子縁組する場合は、親子関係となるため同じ苗字になります。加えて、扶養義務や相続権などが発生することを覚えておきましょう。
養子縁組しない場合は、新しいパートナーと子どもは親子関係ではありません。そのため、母親はパートナーと同じ苗字ですが、子どもは苗字が異なります。
家庭裁判所で子の氏の変更申し立てを行って許可が出れば、養子縁組をしなくても新しいパートナーと同じ苗字に変更することが可能です。
再婚に伴う養育費への影響
養育費の支払いは、法律上の扶養義務がある限り継続する必要があります。ただし、扶養家族の増加などによって、養育費の免除や減額が認められるケースもあります。
親権を持つ人が再婚して養子縁組を行った場合、新しいパートナーに十分な収入があれば、養育費の支払いは免除されることが多いです。養子縁組をしていない場合は、新しいパートナーに扶養義務は発生しないため、基本的には再婚前と変わらず養育費の支払いが続きます。
相続への影響
相続は、亡くなった人の財産や権利などを受け継ぐことを言い、配偶者は常に相続人となります。民法では、被相続人と血縁関係がある子どもは配偶者の次に相続の権利があるとされています。
離婚していても血縁関係のある子どもは、元配偶者の財産や権利を第1順位の相続人として受け継げるのです。再婚した新しいパートナーと子どもが養子縁組している場合は、遺産や生前贈与の相続権が認められます。
新しいパートナーと子どもが養子縁組していない場合は、血縁関係がないため原則相続人にはなれません。
共同親権制度導入後の離婚後の再婚への影響とは
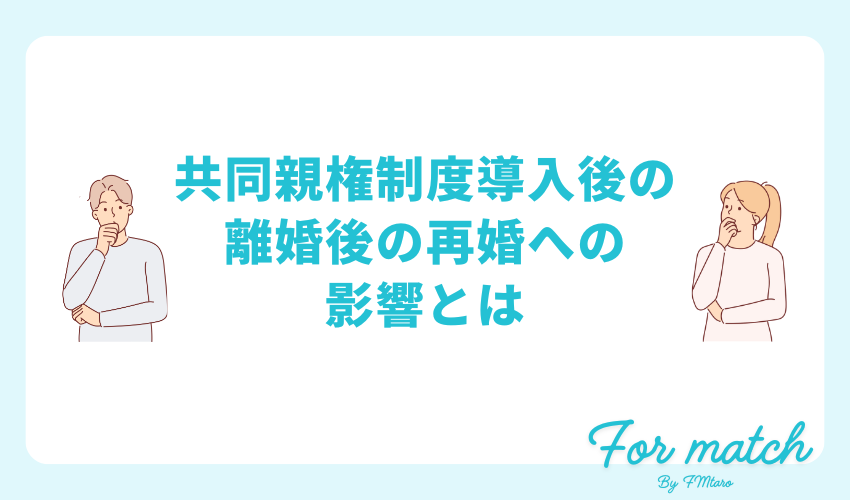
共同親権とは、離婚後も父母共に親権を持ち、子どもの教育や財産管理などの権利・責任を負う制度です。共同親権の制度は令和6年5月に成立し公布されており、令和8年までに施行する予定となっています。
共同親権により、離婚後の金銭面での負担が軽減されるメリットが挙げられる一方で、再婚相手と養子縁組する場合に影響が生じるのではないかと言われています。法律上、15歳未満の子どもが養子縁組をする場合、法定代理人である親権者の承諾が必要です。
共同親権では父母が法定代理人となるため、養子縁組の際に双方の承諾が必要となります。
離婚後に再婚する3つのメリット
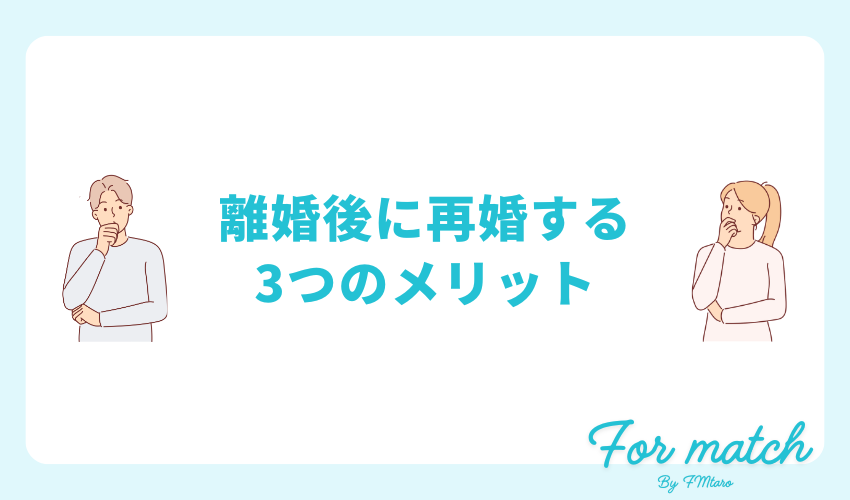
結婚する約4人に1人は再婚者であり、再婚して新たなパートナーと幸せに暮らしている人も多くいます。再婚することのメリットとしては、経済面や精神面での安定、子どもへのプラスの影響などです。
本章では、再婚するメリットについて3つ紹介します。
- 【メリット①】経済的に安定する
- 【メリット②】配偶者がいるという安心感を得られる
- 【メリット③】子どもがいる場合は父親や母親ができる
【メリット①】経済的に安定する
仕事をしている男性と再婚した場合は、世帯収入が増えて経済的な安定を手に入れられます。単純に、収入が二馬力になるため、お金の余裕と気持ちのゆとりを感じられるでしょう。
新しいパートナーの収入だけで暮らしていける場合は、子どもと向き合う時間を増やしたり、趣味に時間を割いたりと、暮らし方の幅が広がります。独身やシングルマザー、シングルファザーのときと比べると、経済力が上がることはメリットと言えます。
【メリット②】配偶者がいるという安心感を得られる
再婚することで、何があっても配偶者がいてくれるという安心感を得られることがメリットです。家に帰れば落ち着く空間があり、家族が待っていることに幸せを感じる人もいるでしょう。
子どもがいる場合は、子育ての苦労を共有したり相談したりしながら、一緒に育てていけます。心配ごとや不安、嬉しいことなどを共有できる配偶者がいるからこそ心が安定し、どのような未来も乗り越えていけるのです。
【メリット③】子どもがいる場合は父親や母親ができる
子どもがいる場合は、再婚することで父親や母親ができることが大きなメリットと言えます。片親の場合、多くの愛情を注いで育てていても、成長過程で片親である寂しさを感じるケースはよくあるものです。
再婚することで、父親と母親がそろって子育てできる環境は、子どもの成長に大きな影響を与えます。たとえば、経済面では我慢を強いることなく、子どもの意見を尊重し応援してあげられる可能性が高くなることもメリットの1つです。
離婚後に再婚する3つのデメリット
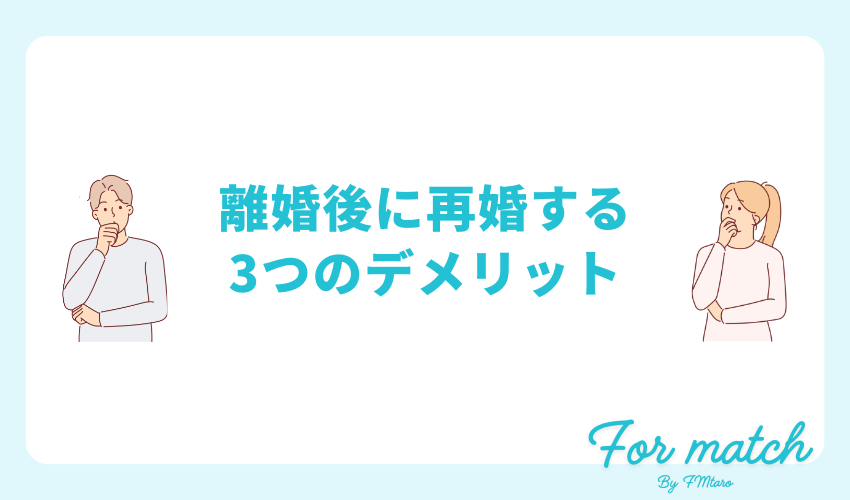
再婚は、経済面や精神面の安定につながるメリットがあると紹介しましたが、もちろんデメリットもあります。再婚するデメリットを理解したうえで、新しいパートナーとの未来を切り開いていく覚悟が大切です。
本章では、再婚するデメリットについて3つ紹介します。
- 【デメリット①】双方の身内の理解を得る必要がある
- 【デメリット②】子どもが不安定になる場合がある
- 【デメリット③】熟年再婚の場合は遺族年金を打ち切られる
【デメリット①】双方の身内の理解を得る必要がある
再婚するデメリットには、双方の身内の理解を得る必要があります。再婚に対してマイナスイメージを持つ人もいるため、初婚のときよりも反対される可能性が高いです。
婚姻の4人に1人が再婚者とは言っても、マイナスイメージを覆すには相当な労力を要します。結婚は、当事者だけでなく家族や親類も含めて親戚となるため、双方の身内からの理解を得ておくほうが円満な関係を築けるはずです。
反対を押し切って結婚することは避け、お互いの家族と話し合って再婚を認めてもらうと良いでしょう。
【デメリット②】子どもが不安定になる場合がある
再婚によって、子どもが精神的に不安定になる場合があることもデメリットです。再婚して子どもの父親や母親がそろうことによる大きなメリットがあるとお伝えしましたが、再婚によって環境や人間関係の変化が起こると、心が不安定になることはよくあります。
再婚する前に子どもと新しいパートナーが一緒に過ごす時間をつくり、信頼関係を築けるように工夫することが大切です。子どもの気持ちを優先し、小さな変化にも気付ける環境を整えておくと良いでしょう。
【デメリット③】熟年再婚の場合は遺族年金を打ち切られる
元配偶者が亡くなって遺族年金を受け取っていた人は、婚姻すると受給できる権利がなくなり、遺族年金を打ち切られてしまいます。遺族年金は、籍を入れない内縁関係であっても受給権が消滅するため、再婚する場合は金銭面に注意が必要です。
遺族年金で受け取っていた金額がなくなると、給与収入のない熟年再婚の場合は、生活に大きな影響を与えるでしょう。経済的な変化によって、喧嘩や離婚へと発展するリスクもあるため、事前に新しいパートナーと話し合っておくと安心です。
離婚後の再婚に関するよくある質問に回答
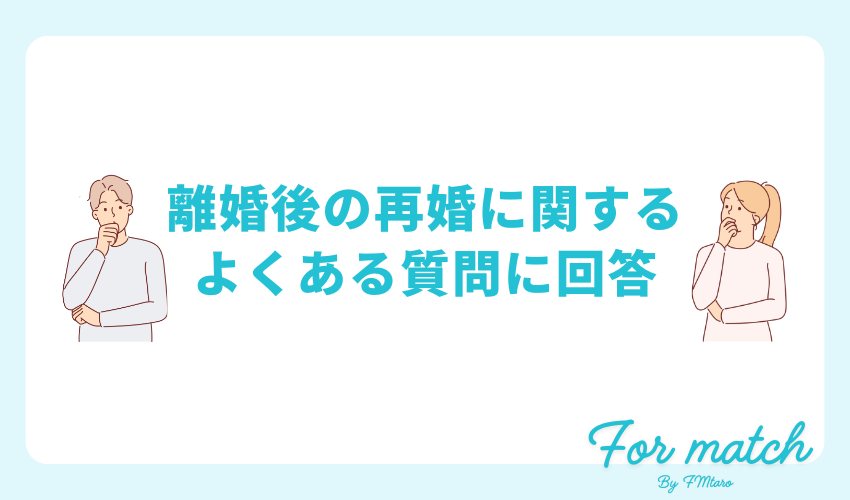
再婚を決意したときに、相手に子どもがいる場合の注意点や年金分割への影響などに疑問を抱く人もいます。本章では、離婚後の再婚に関してよくある質問を取り上げて回答します。
疑問を解決して、幸せな再婚生活をスタートしましょう。
- 離婚後に子どもがいる人と再婚するときの注意点はありますか?
- 離婚後に再婚した場合の年金分割はどうなりますか?
- 離婚後に同じ人と再婚できますか?
離婚後に子どもがいる人と再婚するときの注意点はありますか?
子どもがいる人と再婚する場合は、養子縁組について話し合っておく必要があります。養子縁組をする場合、子どもの親として法的に認められ、養育義務が生じます。
自分が死亡した場合に、再婚相手の子どもにも遺産相続できるようになることがメリットです。一方、養子縁組しない場合は、親子関係とならないため相続権は発生しません。
金銭面や子どもとの関係性など人によってそれぞれであるため、無理に養子縁組する必要はありません。
離婚後に再婚した場合の年金分割はどうなりますか?
離婚時に年金分割をして、受け取っている人が再婚しても受け取れる年金額は変わりません。再婚によって姓や住所が変わった場合は、年金受給者として届け出を行う必要があるので覚えておきましょう。
年金分割をした人が再婚や死亡した場合も、受け取れる年金額に影響はありません。離婚時に年金分割の取り決めをし忘れた場合は、離婚後でも手続きできるので安心してください。
離婚後に同じ人と再婚できますか?
一度離婚した相手と再婚することは可能です。婚姻時に必要な手続きは一般的なものと変わらず、子どもの養育費や面会などに関するトラブルの心配もありません。
離婚後に相手の良さや必要性に気がつき、愛情を再確認して再婚したいと思う人も一定数います。ただし、離婚した原因を振り返り、もう一度同じ人と再婚することについて慎重に考えることも大切です。
【まとめ】離婚後の再婚は幸せをつかむためにも慎重に進めよう
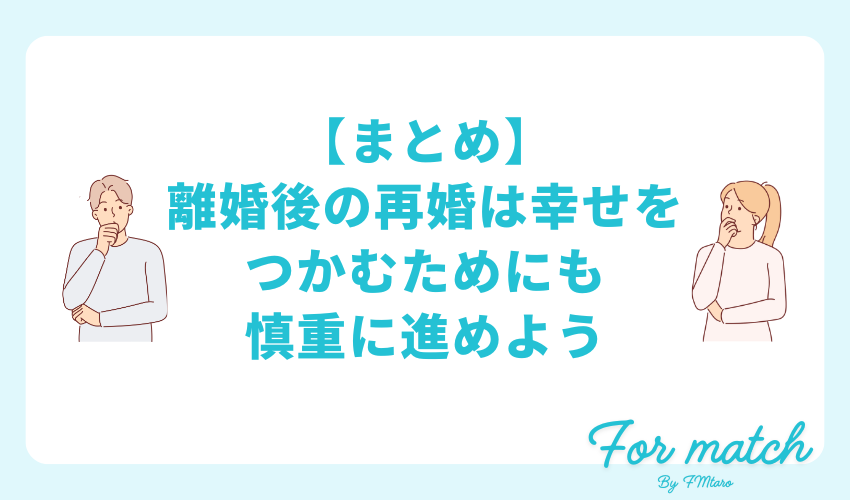
離婚後の再婚を幸せなものにするには、自分にとって何が大切か明確にしておくことが大切です。再婚するにあたって、相手との金銭感覚や身内との付き合い方、子どもに対する認識などを話し合っておきましょう。
手続きや子どもの精神面のケア、身内の理解など注意するべきことは多くありますが、再婚のポイントを押さえて素敵なスタートを切りましょう。









